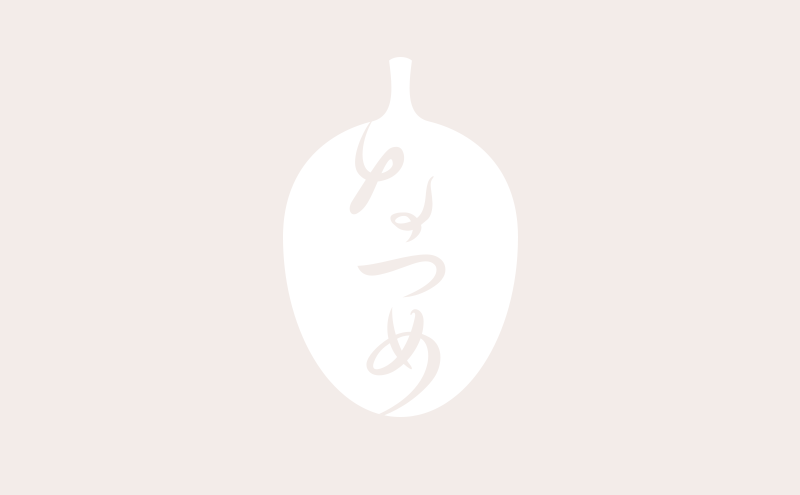なつめ と関係の深い季節の変わり目「土用」は 年4回巡ってきます。
土用とは
昔の人は、私たちの周りの自然を「木」「火」「土」「金」「水」の5つの要素(五行)で見ていました。
春は、草木が芽吹くように勢いよく伸びる「木」のエネルギー。
夏は、太陽がギラギラ燃える「火」のエネルギー。
秋は、実りが凝縮するように落ち着いていく「金」のエネルギー。
冬は、水が静かにたたえられているような「水」のエネルギー。
じゃあ、「土」のエネルギーはどこに行ったの? と思いますよね。実はこの「土」は、それぞれの季節の変わり目に登場するんです!ちょうど季節がバトンタッチする間の期間を「土用」と呼びました。
「土用」の期間は、土のエネルギーが特に強くなると考えられていました。だから、昔の人はこの時期に、土をいじったり、生き物の命を奪うようなことは避けていたんです。ちょっとデリケートな期間だったんですね。
でも、心配ご無用! もし土用に入る前に工事などを始めていれば、土用の期間中もそのまま続けて大丈夫とされていました。また、土用の中には「間日(まび)」という特別な日があって、この日だけは土用の影響を気にしなくても良いとされていたんですよ。※間日については下部に説明あり。
自然のバトンタッチを助ける「土」のチカラ
五行の考え方では、それぞれの季節のエネルギーがスムーズに入れ替わるには、ちょっとした「橋渡し役」が必要だとされていました。春の「木」から夏の「火」へ、急にガラッと変わるのではなく、間にワンクッションある方が自然ですよね。
そこで登場するのが「土」のエネルギー!土は、種が芽を出すように、大きな変化を促したり、守ってくれたりする力があると考えられていました。だから、季節と季節の間で、次の季節へとスムーズにバトンタッチできるように、土のエネルギーが活躍している期間が「土用」なんです。
この「土用」の期間は、一年を5つに分け、さらに土のエネルギーを四季に割り振るために4等分した期間と言われています。なんだか、自然のサイクルって奥深いですね!
年4回巡る土用とはいつ?
年4回巡る土用の期間は立春、立夏、立秋、立冬の前18日間です。
*土用期間は年によって異なります。
*土用の入りの日によっては18日間でない場合もあります。
年によって少し前後します。※下記は2025年の日程です。
冬土用:1月17日 (金) ~2月2日 (日)
春土用:4月17日 (木) ~5月4日 (日)
夏土用:7月19日 (土)~8月6日 (水)
秋土用:10月20日 (月) ~11月6日 (木)
その中でも「土用の丑の日」とは、それぞれの季節の変わり目の「土用」の期間中の丑の日を指します。ですから、これは夏だけのものではないのですが、一般には夏をイメージしますね。(2025年の土用の丑の日は7月19日と7月31日です。)
土用の丑の日は、単なる「うなぎの日」ではなく、体を整える食養生のチャンス。脂っこいうなぎが苦手な方でも、牛肉や黒ごまなど他の食材でしっかり養生できますよ。
土用となつめの関係
土用の時期は「気が乱れやすい」とされ、気血を整える食材が推奨されます。
なつめは、中医学において非常に重要な食材とされており、「一日三粒食べれば歳を取らない」と言われるほど、その効能が重んじられています。その主な薬膳的効能は以下の通りです。
-
・脾胃(消化器系)を補う: 土用の時期は、高温多湿の影響で胃腸が弱りやすいとされています。なつめは胃腸の働きを助け、消化吸収能力を高める作用があります。これにより、食べたものの栄養を効率よく体に吸収し、エネルギーに変える手助けをしてくれます。棗は「脾の果」と伝わるのはその役割のせいでもあります。
-
・気血を補う: なつめは、体に必要なエネルギーである「気」と、体を巡る「血」を補う働きがあります。夏バテで体がだるい、疲れやすいと感じる時には、気力や体力の回復に役立ちます。貧血気味の方にもおすすめです。
-
・精神を安定させる: なつめには、精神を安定させ、安眠を促す効能も期待できます。夏の暑さで寝つきが悪かったり、イライラしたりする時に、心を落ち着かせる効果があります。
-
・体を潤す: 乾燥しやすい季節ではないものの、夏のエアコンによる乾燥や、汗をかくことでの体内の潤い不足にもなつめは効果的です。

なつめを生活に取り入れる
- 実感がないとは思いますが「食べたもので身体は作られる」。よくよく考えるとそのとおりですよね。
- 食物に含まれる栄養がいろんな細胞に関わり、日々私達の身体の中で活動しています。
何年もかかった作られた今の身体はやはり時間をかけて養生する必要があります。
日々、なつめが身近な存在に慣れたら幸いです。
<なつめの使い方>
-
・お茶にする: 乾燥なつめ(なつめチップも可)を数粒、熱湯を注いでなつめ茶として飲むのが最も手軽な方法です。ほんのりとした甘みがあり、リラックス効果も期待できます。
-
なつめいろではティーバッグのお茶をご用意しています。→なつめのお茶
-
・おかゆやスープに入れる: 胃腸が疲れている時にはなつめのお茶、消化の良いおかゆやスープになつめを加えて煮込むのがおすすめです。鶏肉や他の野菜と一緒に煮込むと、栄養バランスも良くなります。
-
・デザートに: 蒸したなつめをそのまま食べたり、甘露煮にしたりするのも良いでしょう。小豆や他のお豆と一緒に煮てぜんざいにするのも美味しいです。
-
・薬膳料理の具材に: 豚肉や鶏肉と一緒に煮込んだり、煮込み料理の隠し味に加えたりすることで、料理全体に優しい甘みと栄養が加わります。
- たくさんのレシピがあります。ぜひ検索してみてください。 → なつめ旬レシピ

土用の時期を健やかに過ごすポイント
冒頭でお伝えしたように、土用の時期は、特に脾胃(消化器系)が弱りやすいとされています。以下のポイントを意識してみましょう。
-
・脾胃を労わる食事: 冷たいもの、生もの、脂っこいものは控えめにし、温かく消化の良いものを摂るように心がけましょう。
-
・甘味と黄色の食材: 薬膳では、脾を元気にするには「甘味」と「黄色」の食材が良いとされます。かぼちゃ、さつまいも、にんじん、とうもろこしなどを積極的に取り入れると良いでしょう。お粥やスープにするのがおすすめです。
-
・湿を取り除く食材: 湿気がこもり、体が重だるく感じやすい時期でもあります。はとむぎ、小豆、黒豆、冬瓜など、利水作用のある食材で体の巡りを助けましょう。なつめいろのおすすめおやつ→ はとむぎミックス
-
・気を巡らせる食材: 気分が落ち込みやすい時は、香りのある食材(しそ、生姜、みょうが、レモンなど)で気の巡りを良くすることも大切です。薬味として加えたり、お茶に入れたりするのも良いでしょう。
-
・適度な運動と休息: 室内で過ごしすぎず、疲れない程度の適度な運動で気の巡りを良くし、心身のバランスを保つことも重要です。
今年の土用の丑の日は、うなぎだけでなく、薬膳の視点を取り入れて、ご自身の体調に合った食材を選んでみてはいかがでしょうか。日々の食事に少し意識を向けるだけで、きっと夏を元気に乗り切る力が湧いてくるはずです。※うなぎはパワーのつく食材ではありますが、調理方法により、とても油っぽい1品でもあります。既に脾胃が弱っている方は、消化の負担にならない調理方法(蒸す・酢の物)などの1品を召し上がるのもいいですよ。
・・・・・・・・・
※間日(まび)
「土用」の期間は、実は「土公神(どくじん)」という、土を司る神様が地上を支配していると考えられていました。だから、土公神様を起こさないように、昔の人はこの時期に、土を掘ったり、穴を掘ったりする作業を避けていたんです。まるで、神様がお昼寝しているときに大きな音を立てないように、といった感じですね。
でも、お仕事は休めない!そこで「間日」の登場
とはいえ、ずっと土いじりの仕事ができないと、生活に困ってしまいますよね。そこで考え出されたのが、特別な日である「間日(まび)」です!
この「間日」には、土公神様が文殊菩薩(もんじゅぼさつ)という仏様に招かれて、天上にお出かけすると言われていました。つまり、神様が地上にいなくなるので、土用のタブーがなくなる、というわけです。これなら、お仕事も安心して進められますね!
★コラム文章 なつめいろ
なつめいろInstagram→natsumeiro